節分の季節には、豆まきと同様に人気がある恵方巻。
多くの人が、子供の頃には恵方巻を食べる習慣がなかったと思っています。
恵方巻きがいつからあるのか、その歴史について話しましょう。
この記事では、恵方巻きの歴史がどれほど新しいのか、またいつから関東地方でも広まったのかを説明します。
恵方巻きは新しい風習?

恵方巻きの起源は、江戸時代から明治時代にかけての大阪で見られる風習に由来していると言われています。
しかし、その具体的な始まりは定かではありません。
江戸時代から明治時代の期間というと、歴史が浅いかどうかは意見が分かれるかもしれません。
日本には室町時代や平安時代から続く伝統も多いですから。
それに比べると、100年以上の歴史があるとしても、恵方巻きが「新しい」と感じる人もいるでしょう。
なぜ恵方巻きが新しい習慣とされるのかについて考えてみましょう。
恵方巻きの広まり方
恵方巻きが広まったのは、昭和初期に行われた販売促進キャンペーンが大きな役割を果たしました。
特に1932年に行われた宣伝広告が、恵方巻きのブームの始まりでした。
昭和時代に流行が始まったため、歴史が浅いと感じる人が多いのは理解できます。
恵方巻きの習慣がしばらく途切れた後、平成に入って再び流行するきっかけがありました。
それは1989年、広島市のセブンイレブン舟入店が恵方巻きを売り出したことがきっかけです。
これが現在の恵方巻きの人気の始まりとされています。
コンビニが流行の起点となったことや、恵方巻きという名前がこの時につけられたことから、平成の風習と見なされがちです。
また、同じ節分の行事である豆まきに比べると、恵方巻きは新しい習慣と感じる理由もここにあります。
恵方巻きはどこから来たの?関東ではいつポピュラーになった?
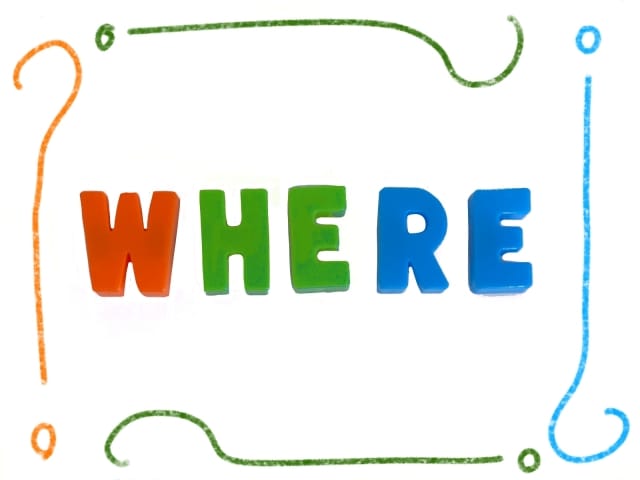
恵方巻きは、江戸時代から明治時代にかけて大阪の遊郭で節分を祝う行事から生まれたとされています。
その当時、遊郭では商人や芸者たちが節分の際に楽しみながら商売繁盛を願ってこの寿司を楽しんでいました。
この寿司は、当時「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」と呼ばれており、今の「恵方巻き」という名称はまだ使われていませんでした。
この食べ方は古くからあるもので、恵方巻きという名前がついたのはずっと後のことです。
関東地方や他の地域への広がりは、平成に入ってからセブンイレブンが行った販促活動によるものです。
そのため、関東地方では比較的新しい風習と感じられることもあります。
恵方巻きを食べる時に願い事を口にすると叶わない?
恵方巻きを食べる際には、静かに食べるのが一般的です。
話すと運が逃げてしまうと言われているからです。
恵方巻きを口にする時は、最後まで何も話さずに静かに食べるのが習わしです。
願い事を他人に話すとどうなるのでしょうか?
通常、日本では自分の願い事を他人に話すと運が逃げるとされています。
そのため、他人には話さない方が良いとされています。
願い事について心配な方は、他人に話さないようにしましょう。
日本全国で愛される恵方巻のいろいろな楽しみ方
恵方巻は関西地方で始まりましたが、今では日本全国でさまざまなスタイルで楽しまれています。
例えば、関東地方では新鮮な海の幸や季節の野菜を使った「海鮮恵方巻」が特に好まれています。
地域によっては、恵方巻の大きさや具材にも多様性があり、丸かぶりで食べることから一部では小分けにして食べる方法もあります。
このような地域ごとの違いは、日本の食文化の豊かさを反映しており、各地で独自の恵方巻を楽しむ風景が見られます。
恵方巻の歴史についてのまとめ
恵方巻の起源は100年以上前に遡りますが、現在のように節分に大規模なキャンペーンが行われるようになったのは21世紀に入ってからです。
そのため、恵方巻の歴史は比較的新しいと言えます。
